R8年度受験予定です。(R7年度は、技術士二次試験に専念することから)
合格率15%程度と難関と言われている試験ですが、建設コンサル勤務のため、合格目指して頑張ろうと思い、受験計画を立ててみます。
難関資格であることと、受験費用も高額です。勉強方法を考えて効率的に学習したいと思い整理しながら勉強していこうと思います。
4択攻略編
基本は、過去問を使用し、以下の項目について、学習する。
1)初期欠陥・経年劣化・構造的変状 を理解する。
2)ひび割れの原因と特徴を理解する。
3)変状を理解する。(特徴、原因や劣化過程、評価など)
出題されている主な変状は、「中性化・塩害・アルカリシリカ反応・凍害・化学的侵入・火災」である。
4)調査方法を理解する。各変状において、特徴的な調査方法を覚える。
5)対策・補修方法を理解する。
論文攻略編
問われている内容を理解する。
[問1] ○○の原因を推定し、その根拠を○つ述べなさい。
[問2] 変状の原因を特定するための調査項目について、○つ述べなさい。
[問3]本橋梁は今後50年間にわたって供用する予定である。○○の変状に対して、それぞれ必要な対策を重要な順に○つずつ提案し、その選定理由を述べなさい。
等の問題傾向となっているため、「原因と根拠」「調査方法」「対策方法」の3項目を整理することができれば、解答の型に沿って解答ができると思いました。
各変状に対して、原因と根拠・調査方法・対策方法を整理する。
各変状に対して、原因と根拠・調査方法・対策方法を整理できていれば、あとは型に当てはめていけば良いため、記述式を解答できるのでは?と考えました。
★塩害
塩害の主な原因は「塩化物イオンのコンクリート中への浸透・混入」による鉄筋腐食である。
塩化物イオンが腐食発生限界値を超えている→塩化物イオン(Cl-)濃度が一定量を超えると「不動態被膜」が破壊され、鉄筋が腐食を開始する。その結果、腐食生成物の体積膨張によって「ひび割れ」「剥離」「断面減少」などの構造劣化が進行し、耐久性が著しく低下する。
主な原因
- 内在塩分:海砂未洗浄、塩化物含有混和材、汚染された練混ぜ水など、打設時にすでに塩分が混入している場合。
- 外来塩分:海水飛沫、潮風、凍結防止剤散布、地下水・河川水の塩分等、外部からコンクリート表面に塩分が供給され、徐々に鉄筋へ到達する場合。
- 防水層の未設置・劣化:建設時・補修時の防水工法未採用や経年劣化により塩分の浸透経路が確保されてしまう場合。
- 鉄筋のかぶり不足:設計ミス、スペーサー誤設置、管理不足等によりかぶり厚が設計値未満、塩化物イオンが早く鉄筋に到達し腐食が進行しやすくなる場合。
- コンクリートの緻密性不足:水セメント比が高い、施工不良、配合設計ミスなどでコンクリートが粗く、塩分・水分が容易に浸透する場合(密実性低下)
- ひび割れの存在:乾燥収縮、施工不良、荷重等に起因するひび割れから、塩分・水分が直接鉄筋付近まで到達する場合。
- 中性化の進行:塩害と相互作用する典型例。中性化が進行したコンクリートはアルカリ性が低下し、不動態皮膜が弱くなるため、塩化物イオンとの併発で鉄筋腐食が加速する。
- 過酷な環境・排水不良:海岸地域、寒冷地、排水設備不良、勾配不良で塩分を含む水たまりが生じる状況。
- 設計・施工不良:上記全てに関係し、防水層未設置、かぶり規定不遵守、粗雑な施工、不十分な維持管理など計画・施工・管理段階での不良要因。
「塩害の原因は、打設時の海砂や塩化物混和材等による内在塩分、海水飛沫・凍結防止剤・潮風等外来塩分の浸透、さらに防水層の未設置・劣化、鉄筋かぶり不足が主要因である。加えて、コンクリートの緻密性不足やひび割れ、中性化の進行、排水不良等も塩化物イオンの鉄筋到達を促進し、塩害を加速する要因である」
主な調査方法
- 目視調査:表面劣化(ひび割れ、剥離、鉄筋露出、錆汁)等の観察で異常箇所を特定する。
- 打音検査:ハンマー等で軽く打撃し、浮き・剥離・内部欠陥の有無を異音で診断する。
- 鉄筋かぶり測定:電磁誘導法やレーダー等で鉄筋までの距離を調査し、かぶり不足の有無を確認する。
- 塩化物イオン含有量試験:コア採取またはドリル法でコンクリートサンプルを取得し、JIS A1154等の電位差滴定法・迅速法・機器分析等により塩分濃度分布を調べる。
- 自然電位法・分極法:鉄筋の腐食進行度(電気的性質)を測定し、腐食状況を評価する。
- 中性化深さ試験:フェノールフタレイン指示薬で切断したコンクリート断面のアルカリ性低下(中性化範囲)を測定、併発劣化リスクを評価。
「塩害調査では、目視・打音検査に加え、鉄筋かぶり測定、塩化物イオン含有量試験、自然電位法・中性化深さ試験等を行い、劣化原因・進行度を把握する。」
主な対策方法
- 表面被覆工法:塗膜防水材、浸透性保護材等でコンクリート表面を被覆し、外来塩分および水分の侵入を遮断。
- 断面修復工法:劣化部を除去後、ポリマーセメントモルタル等で再構築し断面回復と防食性能向上を図る(断面補修)。
- かぶり厚さの確保・増厚:鉄筋かぶり不足部への追加被覆、断面修復や新設時の設計変更等により基準値以上のかぶり厚を確保。
- ひび割れ補修・止水工法:ひび割れ注入・止水材充填により水分・塩分通路を遮断。
- 脱塩工法:電気泳動等によってコンクリート中の塩化物イオン自体を物理的に除去。
- 電気防食工法:外部電源方式や流動陽極方式で鉄筋腐食反応を抑制・停止。
- 排水処理・改善:排水設備新設、勾配調整など水分滞留部への対策。
「対策としては、表面被覆工法や断面修復工法、かぶり厚確保、ひび割れ補修、脱塩工法、電気防食工法等を、劣化状況や部材特性に応じて適切に選定する。排水処理の改善も抜本対策となる。これら一連の調査・対策を的確に組み合わせ、構造物の耐久性を総合的に回復・維持管理する」
★アルカリシリカ反応 ◼︎作成中◼︎
◼︎作成中◼︎
★凍害 ◼︎作成中◼︎
◼︎作成中◼︎
★疲労 ◼︎作成中◼︎
◼︎作成中◼︎
★火害 ◼︎作成中◼︎
◼︎作成中◼︎
解答作成のステップを整理する。
問題文や、条件、写真などを読み取り、以下のステップに沿って、文章を作成していく。
1.変状(外観)の把握
2.調査(机上・実地)、試験
3.原因推定
4.劣化予測、評価
5.補修・補強の要否の判定
6.対策の実施
7.記録とその後の維持管理
解答フォーマット(文章の型)を作成する。
◼︎作成中◼︎
個人的勉強法 論文編1:オリジナルエクセル解答例を作成
技術士二次試験での勉強法がやりやすかったこともあり、同様にエクセルを作成しA41ページで管理・勉強できるものを作成しました。これをブラッシュアップし、勉強していこうと思います。
1000文字版のエクセルマクロシートを作成し、問題文と写真・条件など、解答例を入れ、1枚で勉強できるようにしたものです。これ1枚で勉強できるため効率的だと実感しました。
なお、問題文や問題写真などは公開されていないため、過去問題集などの書籍を購入するしかありませんので、Web上ではボカさせていただいてます。
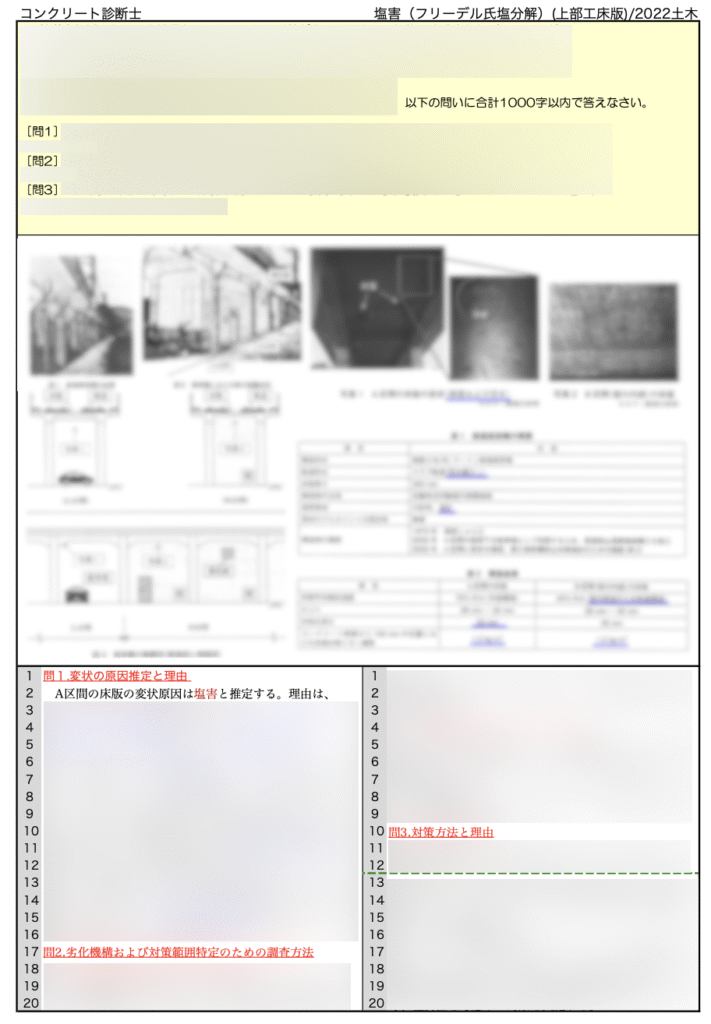
個人的勉強法 論文編2:論文解答例を作成する(9問題文)◼︎作成中◼︎
各主要テーマの論文例を作成してみます。◼︎作成中◼︎
・2024建築:ひび割れ
・2024土木:化学的侵食
・2023土木:塩害凍害
・2022土木:塩害
・2021土木:床版疲労
・2020土木:塩害・再劣化
・2019土木:疲労劣化
・2018土木:ASR
・2013土木:火害


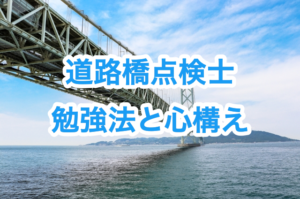
コメント